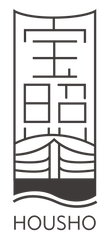雛人形は、主に日本の宮中文化に由来し、平安時代に始まったと言われています。
雛祭りには、雛人形を飾り、それを使って穢れを取り除き、
災厄を避けるという儀式が行われます。
これは、雛人形を使って災厄や不運を身代わりにして、
女の子が健康で幸せな成長を遂げることを願うものです。
つまり雛人形は大切な子供を守ってくれるお守りのような存在。
女の子が無事に成長したところで、本来の役目は終わりになります。
役目を終えた雛人形をそのまま飾り続けることに問題はありません
「雛人形=お子さまの身代わり」という観点から、代々受け継ぐことは
避けるほうがよいと言われています。
祖母や母親の雛人形が家にあっても、それは祖母や母親の身代わりをして、
役目を終えた人形。子供には、「その子の災厄を引き受けてくれる」
新たな雛人形を用意する必要があります。
段飾りを飾るスペースがない場合は、コンパクトな雛人形でかまいません。
その子専用の身代わり人形があるということが大事なのです。
雛人形は捨てるのではなく供養してあげましょう
日本では昔から人形には魂がこもると考えられており、供養をしてくれる神社やお寺は少なくありません。雛人形やぬいぐるみなどの供養を大きく催している神社やお寺もあるので、そちらへ持参するとよいでしょう。
役目を終えた雛人形を供養するイベントが全国各地で行われています。
このようなイベントを利用して合同供養してもらうのがおすすめです。
雛人形を専門に扱う店が協力する感謝祭や供養祭は、人形を大事に扱ってもらえるのでおすすめです。
五月人形や鎧兜なども、人形供養することができます。
神社やお寺などに依頼すれば五月人形を供養することができます。 供養の内容は、寺社でお経を読んでいただき、そのあとに「お焚き上げ」を行います。 これにより、子どもの厄を引き受けた五月人形から魂が抜け、安らかな眠りにつくことができるとされています。
人形の宝照でも、人形供養の代行サービスを行なっております。
ぜひ、ご利用ください。